聞きなれない名前かも知れないが、現在の時刻法(定時法)に対して江戸時代までの時刻の決め方をこう呼んでいる。その訳はこうだ。時刻は次のように決められていた。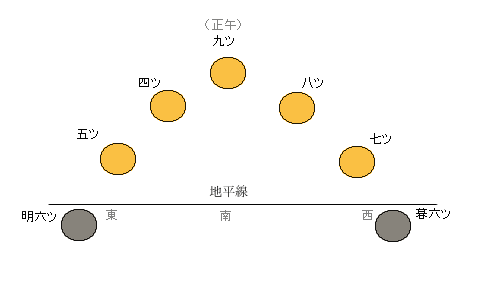 ●日の出36分前(1797年以降は、京都において、太陽の中心が地平線 下7度21分40秒の位置)を明(あけ)六ツ、日の入り36分後を暮(くれ) 六ツと決める。 これが昼夜の境である。 ●昼夜を各々6等分する。この単位が時(とき)または刻(とき)である。 ●昼夜の12時を九ツとして、ほぼ2時間経過するごとに八ツ、七ツ、六ツ、五ツ、四ツとなり、その後九ツに戻る。 この決まりで時刻を決めると、例えば夏を考えてみよう。 昼の長さが、夜の長さよりも長いから一時(いっとき)の長さは昼は長く、夜は短くなる。夏至のころの昼の一時(いっとき)は、2時間40分くらい、冬至のころは1時間50分くらいとかなり違う。その分夜の一時の時間が夏は短く、冬は長くなることになる。 昼夜の一時の時間がこのように一定でないために「不定時法」と呼ばれている。 しかし考えてみると、これが本来の人間の生活に一番合っているのかもしれない。現代では、夜でも明るい電灯があるから、太陽のありがたみが分からないが江戸までの時代は、こんなに明るい照明器具はなかったから、明るい間に、物事を済ます必要があったのだろう。夜明けにあたる明六ツから日暮れにあたる暮六ツまでの昼が人間活動の時間だったといえる。 正確に言えば、毎日昼夜の時間が変化しているのだが、毎日時刻を変えていくのも大変である。そこで、1年を24等分して立春から大寒までの二十四節気というものを考えた。それぞれの始まりに時刻を定め、同じ節気中はその時刻体系を使用した。この不定時法は明治5年まで使われていた。 当時の暦学者は1日を100刻(こく)とした定時法で天体の位置計算をしていた。 「一刻(いっこく)を争う」という言葉の起こりはここにあるらしい。 だから、「刻」を「こく」と読ませたり、「とき」と読ませたり、その時場所によって意味が違ってくる。約2時間であったり、14〜15分だったりするので注意が必要だ。 理科年表には、「夜明」「日暮」として、太陽の位置が地平線下7度21分40秒の時刻を載せているので、興味のある方は見てみるといい。 自然の明かりを大事に思う心は、旧暦(太陰太陽暦)を生んだ。 ひとつきのはじまりの一日は、新月の日と決め、月の満ち欠けを暦の基本に置いていた。だから、15日と言えば、必ず満月であり、夜もやや明るくなり、気分も普段とは違っていたのかも知れない。ただ、月の満ち欠けだけで暦を作ってしまうと、月の満ち欠けは約29.5日で繰り返すため、1年という周期で見た場合、季節がしだいにずれていってしまい、農作業など生活に不便が生じることになる。そこで、1年の長さは太陽の動きで決めていた。これが、旧暦(太陰太陽暦)である。ちなみに旧暦の年初は立春である。この方が年の初めという感じがしていいように思う。太陽暦の1月では、これからまだ、一番寒い大寒を迎えなくてならないからだ。 不定時法と旧暦というのは、現代の生活には不便かも知れないが、人間本来の時間体系なのかもしれないと最近思うようになってきた。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
「二十四節気」
|