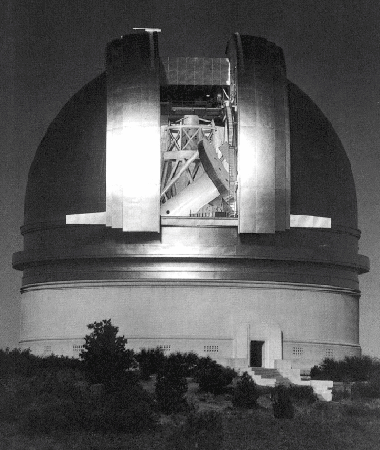
パロマー山天文台
19世紀半ばから終わりにかけて、各地で大口径屈折望遠鏡が作られた。この背景には光学理論とガラス製造技術の裏付けがあった。ドイツのガウス(1777〜1855)はレンズ計算の基礎理論を作り上げ、ザイデル(1821〜1896)は光学系がもつ悪い癖(収差という)について研究していた。ザイデルは星の像が鮮明に見えるためには、色消しのほかに5つの収差を取り除くべきであると説いた。現在、ザイデルの5収差として知られている。
大口径の屈折望遠鏡を作るには、ガラス製造技術の向上が、もう一方で必要であった。
ドイツのフラウンホーファは、ガラス製造技術と光学理論を心得ていた数少ない科学者だった。彼は天体観測でも業績を残している。太陽光線をプリズムに通して見たとき、その中にたくさんの暗線(フラウンホーファー線と呼ばれている)を見つけている。これは、後に、星の光をスペクトルに分けて成分を分析する手段として使われるようになる。天体分光学の始まりである。
このような時代背景のもとに、1840年、モスクワ郊外のプルコバに口径38cmの屈折望遠鏡が設置される。続いて1843年にはアメリカのハーバード大学にも同等の望遠鏡が設置された。しかし、それ以上の大口径の出現には、アメリカのクラークを待たねばならなかった。
クラークはもともと肖像画家であったが、ハーバード大学の38cm望遠鏡を見てから画家を辞めてしまう。そして、レンズ製造一筋に生きるようになる。彼が取り組んだ最初の望遠鏡はミシシッピー大学から依頼を受けた47cm望遠鏡であった。1861年のことである。クラークは望遠鏡のテストのために、全天で一番明るい星シリウスを使った。当時、ベッセルによって、「シリウスが奇妙な動きをしているため、近くに別の星があるのではないか」と予言されていたのだ。実際、製作した望遠鏡で調べてみると、シリウスから角度で約8秒離れている暗い星を捉えることができた。その明るさはシリウスより10等も暗い。そのため精度のよいレンズが要求されていたのだ。
今までのレンズでは、明るいシリウスの背後にうずもれてしまって、確認できなかったのだ。続いてクラークはリック天文台の91cm、そして1897年のヤーキス天文台の101cmへと進む。屈折望遠鏡はここにきて限界に達した。製作できる大きさの限界である。
1880年頃から肉眼での観測に代って、写真が天体分野にも登場しはじめた。屈折式望遠鏡では、色のにじみも完全には取れなかったり、写真感光能力の高い紫外線がレンズで吸収されたり、などの悩みがあった。
一方、反射鏡の方はどうかといえば、金属鏡である限り、その成分の銅が短期間で錆びて鏡の表面が曇るという問題があって、製作が小康状態になっていた。また、金属鏡の反射率が50〜60%程度というのも問題であった。この突破口は、ガラス表面に銀の塗膜を作る技術開発によってもたらされた。銀の反射率は95%以上ある。
金属鏡の50%から銀の反射率95%は、見える明るさを約2倍にした訳だから画期的な発明と言える。1856年にドイツのシュタインハイルによって、はじめてガラス表面に銀塗膜をほどこした望遠鏡が作られる。こうして、第2の反射望遠鏡時代が、20世紀に入り幕開けする。
この先導役を努めたのが、アメリカの天文学者ヘールであった。大口径反射望遠鏡にかける彼の熱意はすごい。150cm反射鏡に始まり、1918の250cmへと進む。これだけの大望遠鏡製作には莫大な資金が必要だ。その資金を彼の友人であるフッカーに出資させた。
2つの望遠鏡は、アメリカのウィルソン山天文台に納められフッカー望遠鏡と呼ばれている。
この2.5m反射望遠鏡で大きな成果をあげたのが、あのハッブル(1889-1953)だ。宇宙の膨張法則、通称「ハッブルの法則」を発見した人だ。この頃には、星の光を分析して、星の速度を測る方法が考え出されていた。望遠鏡に分光器を付けてスペクトル写真を撮る。それを地上の基準スペクトルと比較すると、ある星は全体に赤側にずれ、ある星は青側にずれている。このずれ具合を測定することによって、星の速度が計算できるのだ。いわゆる「ドップラー効果」を利用している。救急車がサイレンを鳴らしながら近づいてくるときは、音が高く聞こえ、通り過ぎていったとたんに音は低くなる。これと同じことが光でも起こるのだ。
遠ざかる星は赤っぽくなり、近づいてくる星は青っぽく見える。
1929年、ハッブルは、スライファーが写した18個の銀河のスペクトルを分析して、その速度を求めた。距離は、銀河の中にある特別なセファイド型変光星の観測から得られる。
 ハッブル(1889〜1953)
ハッブル(1889〜1953)こうして、ハッブルはセファイド型変光星を利用して銀河までの距離を求め、速度はスペクトルのドップラー効果から求めることができた。そして、銀河までの距離とその速度の関係をグラフに描いてみた。一直線上に各銀河が乗っているではないか。遠い銀河ほど、速く遠ざかっているのだ。
これが膨張宇宙のはじめての提示であった。
ハッブルの観測した銀河は一番遠いもので約600万光年の距離であったが、現在ではその数百倍遠くの銀河まで観測されていて、ハッブルの法則が成り立っていることが分かっている。遠い銀河では、セファイド型変光星も見分けがつかない。そのときは、「銀河全体の明るさはどの銀河もだいたい同じ」と仮定して距離を推定したりしている。ウィリアム・ハーシェルの銀河模型を考えた場合の「星はみんな同じ明るさ」という仮定と似ている。距離測定法は、この他いろいろ考えられているが、一つの方法ですべてをカバーできる所までには至っていないのが現状だ。
| 銀河の距離を測る:セファイド型変光星 セファイド型変光星は、明るさを規則的に変える変光星の一つである。 この星は1〜50日の周期で規則正しく縮んだり、膨らんだりしている のだ。そのとき明るさも、1等級くらい変化する。アメリカの女性天文 学者リービットは、隣のマゼラン銀河の中にある多くのセファイド型 変光星を観測しておもしろい事実を発見した。マゼラン銀河までの 星々までの距離はほとんど同じと考えてもいい。 同じ距離の同じ明るさの星は、当然のことながら、同じ明るさにえ るだろう。それなのに、周期の長い変光星ほど見かけの明るさが明 るいのだ。これは、星そのものの明るさ(絶対等級という)が違ってい るからに他ならない。絶対等級というのは、星を一定の距離(32.6光 年)に置いたときの明るさで、星どうしを比べるときにはどうしても必 要な明るさだ。「セファイド型変光星は、変光周期が長ければ、絶対 等級が明るく、短ければ暗い」という単純な性質を持っているのだ。 変光星の周期を観測から決めてやると、絶対等級が分かる。光の明 るさは、距離の二乗に反比例しているから、星が遠く離れるほど暗く なる。だから、「みかけの明るさ」と、「変光星の周期から求めた絶対 等級の明るさ」から銀河までの距離が求められるというしかけなのだ。 |
遠くの銀河ほど遠ざかる速度が速いというと、まるで、われわれの銀河系が宇宙の中心にあるように思えてくるが、そうではない。地球中心の天動説の誤りを繰り返してはいけない。むしろ、「宇宙にはどこも特別な場所がない」と考える方が自然ではないのか?ここで起こっていることは他の銀河でも同じように起こっている。どの銀河から見ても他の銀河は遠ざかっていると考えるのだ。風船の上に銀河の印をつけ、それを膨らませてみよう。
風船が膨らむにつれて、お互いの銀河の位置がどの銀河から見ても遠ざかっていることが理解できる。このように宇宙全体が膨張していると考えると、つじつまが合ってくるのだ。
膨張宇宙の話から、話を元に戻すことにしよう。1930年に入ると、鏡のメッキとして銀より長持ちするアルミニウムが使えるようになる。ヘールは2.5m望遠鏡でも満足できなかった。そして、最後の計画に着手する。直径5mという途方もない巨大反射鏡だ。
1934年に1枚板の5m鏡は鋳造されたが、望遠鏡を載せる台、そして観測ドームなどすべてが完成するのは、それから14年後の1948年であった。
第二次世界大戦が終結してから3年目である。ヘールは、その完成を見ることなく、完成の10年前にこの世を去っていた。パロマー山5m望遠鏡、通称「ヘール望遠鏡」は、1976年、旧ソ連コーカサスのツェレンチュクスカヤに6m望遠鏡ができるまで、世界一を誇っていたのだ。
| 「ビッグ・バン」を考えた人 「不思議の国のトムキンス」などで知られたロシア生まれのアメリカの物理学者ジョージ・ガモフ。ガモフ全集という物理を楽しく読ませる本が、日 本でも翻訳されていて、科学嫌いの人でもきっと引き込まれていくに違いない。アイザック・アシモフなどにも通じる所がある。 そのガモフが、宇宙のはじめを「原始火の玉」と考えた論文を発表した。それに対して、当時ライバルの理論であった定常宇宙論の提唱者の一人であるフレッド・ホイルが「この理論は自爆ものだ!」と軽蔑の意味も こめて言ったのが「ビッグ・バン」の名前の起こりだという。ビッグ・バンの証拠として最も有力なものが、「宇宙3K背景輻射]として 観測されている。高温の火の玉宇宙が、今は冷えて絶対温度3度 (−270℃)の雑音が宇宙にあまねく満たしているというのだ。 |